| |帰国して 一覧|2019年 一覧| | |
| 養蜂家の蜂貸しビジネス |
||||
|
||||
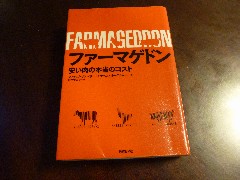
表題について外国の話ですが、半年前読んだ本に詳しく出ていたことを思い出しました。 『現在、養蜂家の多くは、ハチミツの生産より受粉サービスでお金を儲けている。 略 ハチサービスの利用料は上昇する一方だ。2004年に比べるとその金額は3倍になり、今では巣箱を1つ借りるのに180ドルもかかる。中には、ハチのレンタル料が高騰したせいで。農業をやめた人もいる。』 出典 『ファーマゲドン 安い肉の本当のコスト』 フィリップ・リンベリー|イザベル・オークショット 2015年2月第1版 発行日経BP社 本の表題 ファーマゲドンとは、 ファーム(農業)がもたらすハルマゲドン という意味です。 もうひとつ上記の本から引用します。 『毎年、晩冬や早春には3000台ほどのトラックが米国を横断し、カリフォルニアのセントラルバレーまで約400億匹のハチを運ぶ。南北が400マイルに及ぶその広く平らな谷間には、約60万エーカーのアーモンド畑があり、世界のアーモンドの80%が生産されている。その受粉はまさに史上最大規模の受粉イベントである。その費用は高額で、現在、カリフォルニアの栽培者は、年に2億5000万ドルをハチに費やしている。これは、農業の持続不可能なやり方のせいで、自然のサポートシステムが壊れていくもう一つの事例である。』 最初にこの本を読み始めてすぐに、あれっ この作者は西洋の人とは思ったけれど、いったいどこの国の人?とおもいました。懐かしいイギリス人のしゃべりかただったのです。 やっぱりねと確かめた後、内容も彼の国のスーパーマーケット(ウェイトローズ、センズベリー、テスコ などなど)の名前や私のお気に入りのテレビ番組を持っていたシェフのヒュー ファーンリー=ウィッティングストールの名やイギリス各地の地名がでてきて、イギリスに帰ってお話を聞いている様な心持になりました。しかし、内容は人類の恐ろしい未来が良く見えて来るようで、私はしばしば読み澱んだものです。自然がどんなに人の営みによって破壊されているか、もっともっと現実を知らなければと思いました。この本を是非たくさんの人に読んでいただきたいです。 日本でも ところで、蜂を授粉用に使っている実例がテレビにでてきました。NHKEテレ『野菜の時間』でビニールハウスの中でセイヨウマルハナバチを飼っている話です。 「以前はナスの授粉を人手でホルモンを使ってやったこともあったけれど、とてもたいへんだった。ハチが飛びまわって受粉すると、もう一つの効果がある。ホルモンを使った時は花がらが落ちないで実にはりついたままになり、そこだけ光が当たらないでナスの色が全体に着かなくて困った。しかしハチが受粉させると花がらが時間とともに落ちて好都合だ」 ということでした。(2018年1月7日 再放送2019年1月20日) 師匠の話に、この近所でビニールハウス内の植物の授粉をハチでやっているところがあるとちらっと聞いたのですが、確認するチャンスがいまのところありません。ハウスにつなげた小さなトンネルがあって外の巣箱からハチが出入りしているのを見たということです。その人にハチを育てないかと勧めてみたら、難しいからやらないというお返事だったとか。 身近に受粉サービスは行われているのに私は知らないだけだと悟りました。 なお『ファーマゲドン』には、大規模な工場式農場の出す汚物のことや、効率を求めるあまり取り返しのつかないほどの多くの問題点がある話や、あるいは魚の養殖の問題など、多岐にわたって詳しく書かれています。是非読んでいただきたいです。そして消費者として現実を知って欲しいです。 日本の豊かで有り余っているように見える食の本当の姿が、オリンピックの食材からあぶりだされてきた今こそ、みんなで学び、生産者に要求し、健全な食材を育てていきたいです。 |
||||
|
| |
| |帰国して 一覧|2019年 一覧| | |
| 福岡県 |
